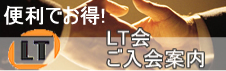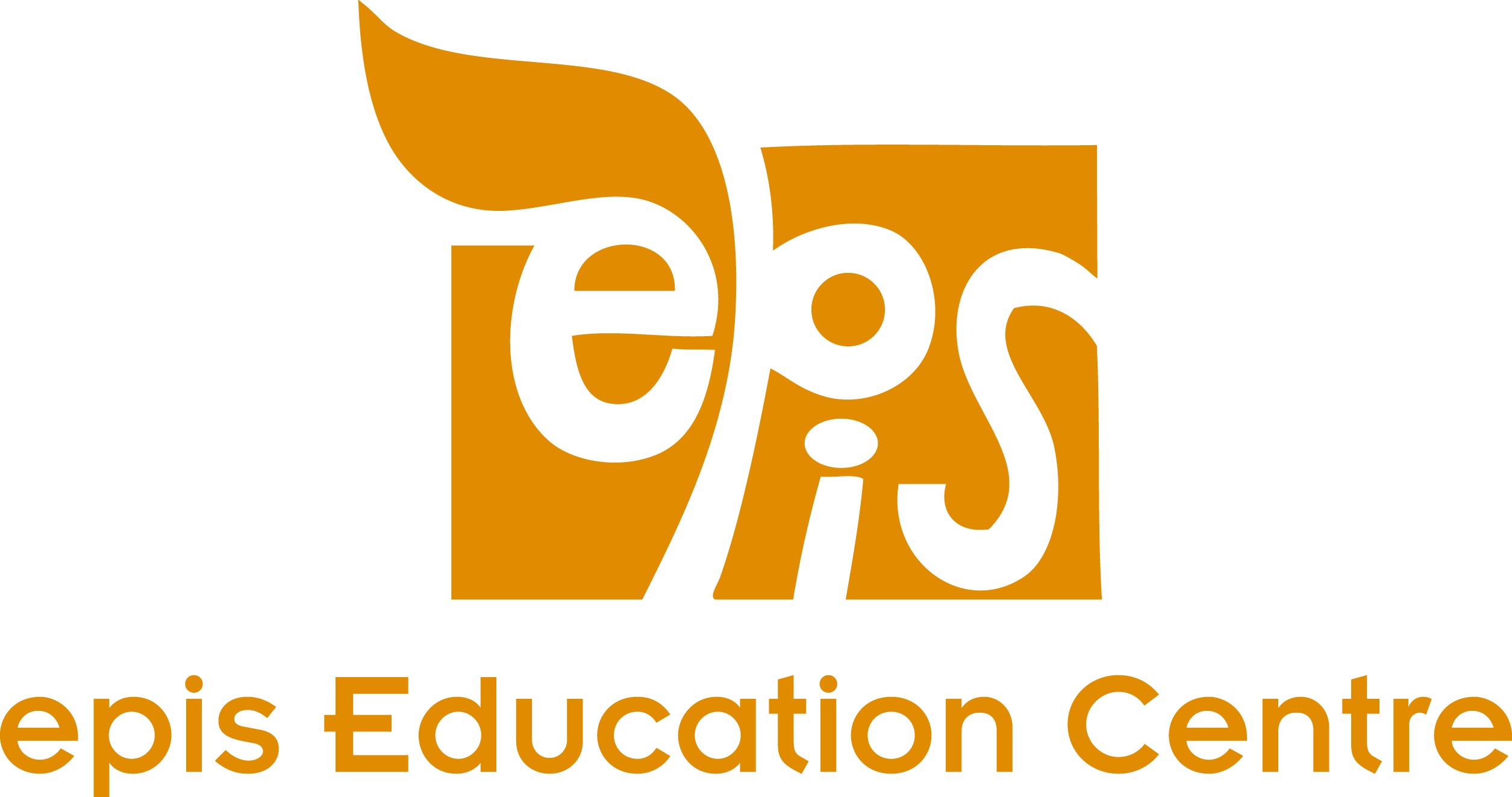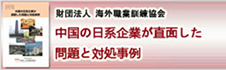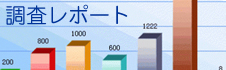2009-05-08
「LT会」会報(第8-01号、総26号)
08年度中国経済の行方(バブル崩壊の年になるか)
―――バブル崩壊に備えたリスクマネジメントは?―――
配信者:上海良図商務諮詢有限公司
「LT会」会員各位
新年明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。本年も引き続きご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。
今年はいよいよ北京オリンピック開催年となり、北京はオリンピック関連イベントで盛り上がっているようだが、一方で上海を始め他地方ではいま一つ盛り上がりに欠けており、それよりも不動産取引の低迷から価格の下落傾向、果ては一部不動産仲介業者の閉店の話題が世間を賑わしている。
昨今の中国経済はかつてのアメリカや日本のバブル期経済と類似しており、これまでのような中国経済の高成長は限界に来ているのでないかと憂慮する声もちらほら聞こえてきている。
20世紀前半、第一次世界大戦後のアメリカは空前の経済的繁栄を遂げ、一般民衆の投資熱を受けて株価が上昇し続けた。だが1929年10月24日(いわゆる暗黒の木曜日)の株価大暴落により、バブルは崩壊し、たちまちのうちに世界恐慌に突入した。
又日本は1986年頃から地価の上昇傾向が顕著になり、87年からは株価が大幅に上昇し、土地の値段は永久に上昇し続けるという土地神話に支えられ、株、その他の資産とも膨らみ続けたが、90年から株価と地価の急激な下落によりバブルが一気に崩壊した。
アメリカの有名な経済学者ガルブレイス博士はその著『大崩壊』で、人間は60年から100年に一度世界のどこかで狂乱の投機熱に浮かされると言っている。
斉藤精一郎著の『金融恐慌と三つのバブルの物語 大崩壊が始まる時』には、世界のバブルに共通する特有の現象が次のように纏められている。
1.国の経済全体として金が余っている。
2.国民の多数が参加する投機ブームが一定期間継続する。
3.特定の投機対象に対して「値上がりし続ける」という神話が生まれる。
4.成金が誕生し、拝金主義が横行する。
5.贅沢品嗜好が高まり、物価上昇と資産(株価と不動産価格)の上昇が始まる。
6.モラルが退廃(モラルハザード)し、汚職、詐欺的商法等が横行する。
7.世界経済における自国の優位性について自信過剰となり、高慢になる。
今の中国の経済情勢は、金余り現象、国民の多く(資産家でもない極普通の庶民までも)が不動産、株投機に奔走し、土地神話が生まれ、株価と不動産価格が上昇し続け、贅沢品の売れ行きが好調になる等、上記のバブル傾向と正に合致している。
日本のバブル崩壊は1990年から株価が下落し始め、当時の大蔵省と日銀が「不動産総量規制」を実施したことで、不動産の流通が止まってしまったことにより、不動産価格までもが暴落し始めた。
中国では上昇し続けていた株価に昨年末頃から下落傾向も見られている。又不動産購入に対する融資規制と総量規制により、不動産売買熱が急速に沈静化している現象は、日本のバブル崩壊時の現象とも類似している。深センの不動産市場はかなり冷え込んでおり、昨年第4四半期の不動産価格は約20%も下落した。様々な規制によって不動産投機のうま味が減り、国民の不動産に対する投資意欲が急速に冷え込んでいる。いつ株価と不動産価格の暴落が始まってもおかしくないのではないか?
現在、中国の金融引締めと総量規制により、今後日本企業は以下のリスクに直面することが想定される。
1.自動車などの高級品の売れ行きに急ブレーキがかかる。
2.新築住宅と公共工事の減少による周辺産業への影響。
3.金融引き締めにより企業の運転資金調達に支障が生じることにより、売掛債権回収が困難になる。中国特有の三角債問題が再燃する。
4.景気のトーンダウンにより、中国市場向けの商品に不良在庫がでる。
5.過剰な設備投資により、設備の稼働率が低下し、資金繰りが悪化する。
6.人民元レートの上昇によりメイド・イン・チャイナの国際競争力が低下する。
7.原油価格の高騰による原材料の価格上昇や食糧不足による価格上昇で、高インフレに見舞われる。
上 上記リスクも含め、各企業は有事の対応策の再検討が必要となる時期が来ているのではないだろうか?例えば中国市場向け販売商品の設備投資を控えめにし、国内向け商品だけではなく、輸出製品の生産を拡大することもリスク回避の選択肢の一つとなる。
昨年度人民元の対米ドルレートは6.9%も上昇したにもかかわらず、現状中国の貿易黒字削減の目処が立っていないことから、引き続き人民元レートの上昇が予測される。人民元レートの上昇に対する為替リスクのヘッジも益々重要な課題となっている。三角債の再燃に備え、売掛債権の回収も緊急且つ重要な課題となり、売買契約書の見直し、売り掛けサイトの短縮による売掛債権回収を強化することも視野に入れておくべきだろう。
以 上