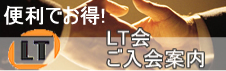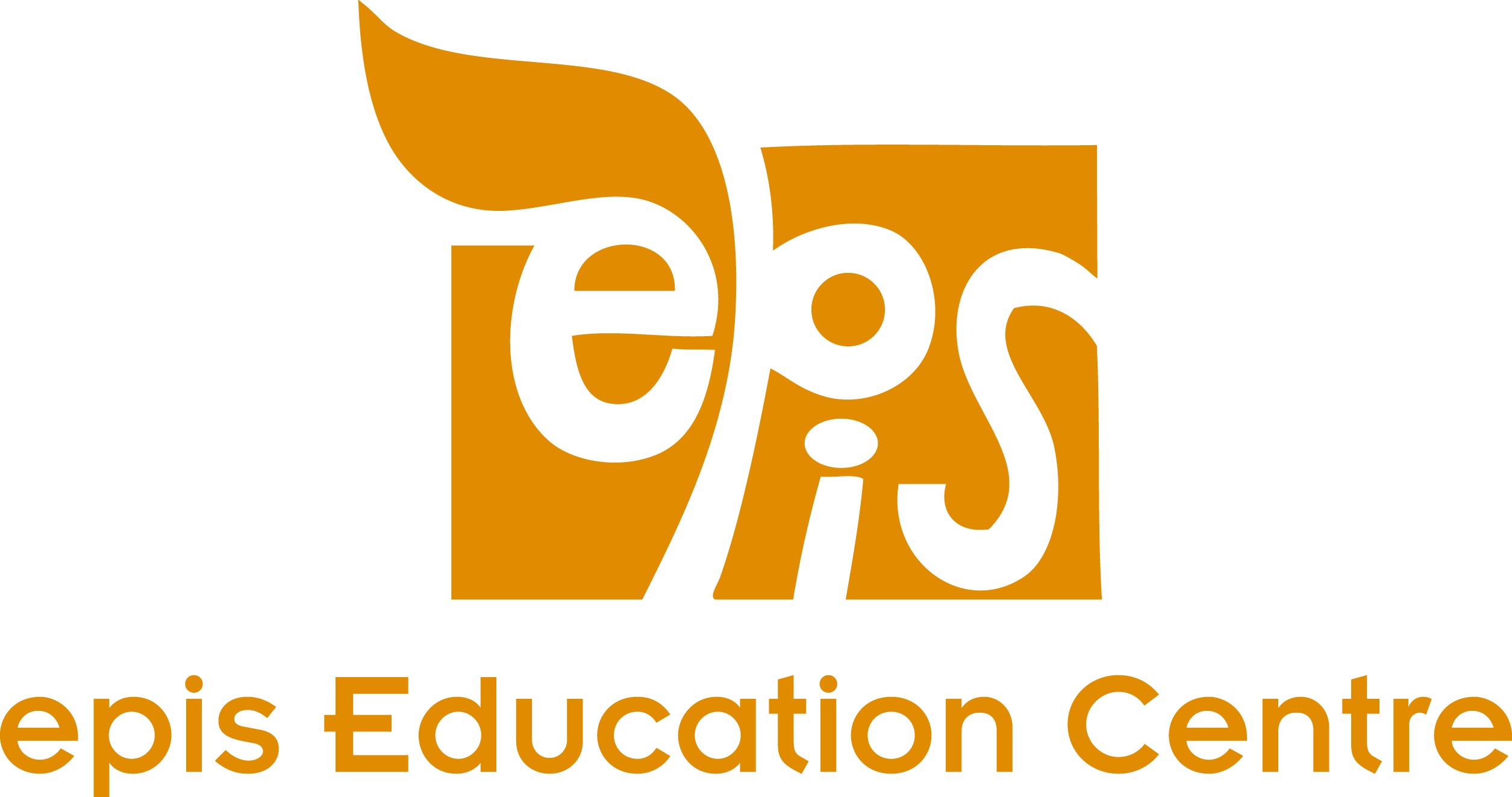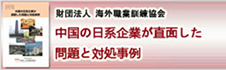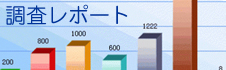2008-03-06
世界的経済危機の影響を受け、少なからぬ在中日系企業が操業調整や人員削減、最悪の場合中国からの撤退までも余儀なくされている。弊社でも昨年上海・江蘇・浙江地域の日系企業数社の会社清算業務を取り扱ったが、一連の清算業務の過程において、各種登記・許認可の取消や抹消手続きだけでも通常半年はかかるのだが、従業員の解雇という問題が順調に進むか否かが清算業務全体に大きく影響することを、改めて実感させられている。
ご承知のとおり、中国では2008年1月1日より、労働契約法が施行され、労働者の権利が一層保護されるようになったと同時に、企業にとっては従業員解雇に関わるコストが大幅に増大することになった。又、新しい調停仲裁法で“仲裁の無料化”の原則が規定されたことで、労働者の企業に対する訴えにますます遠慮がなくなった。最近もある日系メーカーの事例から、解雇や会社清算時に労働争議を回避するためには、日常の労務人事管理を強化する必要性を改めて感じた次第である。
労働争議が発生しやすい問題点は概ねいくつかのポイントに集中している。主に労働契約の解除、経済補償金の支給、社会保険、労災、秘密保守条項、拘束期間等である。これら日常の人事管理において見落としがちなものの中から、特に注意を要するものをピックアップしてまとめてみたので、ご参考にしていただければ幸いです。
1、 労働契約書の内容
① 試用期間
“試用期間”と“正式採用”は二つの別々の法律関係ではないことに注意する必要がある。試用期間は労働契約期間に含まれなければならない。また、試用期間中でも社会保険には加入していなければならない。
② 給与賃金
必ず現地の最低賃金基準を満たしていること。また社会保険の保険料は、原則として労働契約に盛り込まれた税引き前賃金の金額が基礎となるが、地方によって社会保険料の上下限が異なるので注意が必要である。
③ 労働契約の継続更新
労働契約法には、“従業員と一ヶ月以上労働契約を交わしていない場合、会社は従業員に2倍の賃金を支払わなければならない”となっている。この規定に“契約の継続更新”の場合が含まれるか否かについては議論が分かれるところだが、不要な面倒を避けるためにも、契約期間満了前に書面で契約継続についての通知をし、その証拠を残しておくのが望ましい。もし従業員が故意に継続契約の署名を引き延ばすようなことがあっても、その責任の所在を明確にすることができる。
2、 社内規則の整備
きめ細かな社内規則を整備しておくことで、万一労働争議が起こったときの備えとなる。たとえば、就業規則に、残業の事前申請許可制を盛り込んでおくことで、労働契約を解除する時になって従業員が以前の出勤記録を盾に会社に残業代の支払いを要求するようなことのないようにできる。
労働争議の解決に際しては、会社が原告であれ被告であれ、従業員の合理的要求に対して、会社が反論に値するだけの証拠を提出できない場合、即ちその要求が成立することが法律で認められている。会社は普段から従業員の出勤記録や規律違反記録などの証拠を収集して人事記録をきちんと保管しておくことが肝心である。
3、 社会保険の脱退
① 脱退手続き
地方によって毎月の社会保険脱退日の制限が異なるため、従業員の解雇に伴う社会保険脱退手続きの際に注意が必要である。できるだけ早めに脱退手続きをするようにして、余計な経費支出を回避するようにしたい。
② 社会保険料の追徴
労働関係の解除に際し、会社が当該従業員の社会保険料を2年以上支払っていた場合、それ以前の未加入部分についての追徴はされないが、そうでない場合は、以前の未加入期間についても全額(会社負担の部分)支払わなければならない。但し、会社が当該従業員の社会保険料を2年以上納めていた場合で、従業員が未加入期間の社会保険料を全額自己負担で支払いを希望する場合、会社はその手続きだけをしてあげることができる。
③ 従業員個人への補償
前項で未加入期間の社会保険料を支払う場合、会社負担部分はもちろん、個人負担部分も就業期間中同様、会社が賃金等から天引きして代納しなければならず、従業員個人に支給されるのではない。経費節減策の一つとして、会社が何らかの補償金(未加入期間の社会保険料より少額であることが望ましい)を従業員個人に支払うことで、当該従業員が未加入期間の社会保険料の支払いを希望しないよう、従業員と協議することも考慮できる。
4、 年次有給休暇の段取り
労働関係の解除までに未消化の年次有給休暇が残っている従業員に対し、できる限り労働関係解除までに休暇を消化し終えるように段取りすることが望ましい。未消化の有給休暇が残っている場合、賃金の3倍を支払わなければならないことになる。
5、 定年退職後の再雇用者の解雇
① 定年退職後に再雇用した従業員は、労働契約ではなく、労務契約を締結することになる。この場合、労働契約法に定める社会保険や経済補償金等の適用外となる。
② 入社時に定年退職年齢に達していなくても、労働関係を解除する時点で法定退職年齢に達している場合は、経済補償金を支払う必要はない。
③ 定年退職者は労働契約法に定める次の3つの場合を除き、同法の適用を受けない。A.最低賃金規定に違反する場合。B.労働時間の規定に違反する場合。C.労働保障に関する規定に違反する場合。
6、 清掃人等パート勤務者の解雇
労働契約法では同一雇用主の下での一日の平均労働時間が4時間を越えず、1週間の労働時間の合計が24時間を越えない者をパート勤務者と定義している。上記労働時間を越えた場合、経済補償金を計算する時、労働契約を交わしていない正社員と同一に処理される恐れがあり、その場合経済補償金を支払わなければならない。
7、 労災認定(通勤途中を含む)
労働争議で多くみられる事案の一つに、労災補償の請求がある。会社としてはこれに関する社内規則を整備し、労災事故が発生した時に速やかに労災か否かの判定を行い、特に通勤途中などで明らかな労災と判定されにくい部分まで安易に労災として処理しないようにしたい。
8、 重要部署の業務引継ぎ
会計、出納、倉庫管理、営業等会社にとって重要な部署の業務引継ぎは後日の日常業務や清算業務に直接影響するため、非常に大切である。会計責任者には原価計算や税金の月次報告等を詳細に引き継ぐ必要がある。営業社員は労働関係を解除するまでに未収金を回収させておかなければならない。これらの業務引継ぎがきちんと完了してから経済補償金を支払うようにしたい。
9、 研修協議に定める拘束期間
拘束期間が定められている場合、労働契約期間より拘束期間が長い場合は、拘束期間を優先する。また、秘密保持や競業制限に関する条項違反に対する違約金を設定する時は、そのリスクは従業員と会社の双方にあるということを十分考慮しておかなければならない。必要以上に高い違約金の設定は、従業員を解雇する際のコストを高くすることになりかねない。
10、経済補償金
① 勤続年数の計算:今の会社での勤続年数が一年以上の者には一ヶ月分の賃金に相当する金額を、6ヶ月以上1年未満の者は1年と計算し、6ヶ月未満の者には半月分の賃金に相当する経済補償金を支払う。
② 毎月の賃金がその地方の前年度の平均賃金の3倍を上回っている者に対する経済補償金は、平均賃金の3倍の金額とし、その支払い期間の計算の根拠となる勤続年数は最高12年とする。賃金が平均賃金の3倍未満の場合は勤続年数12年までの制限を適用しない。
③ 平均賃金とは、労働関係を解除する前の12ヶ月間に支払った、残業代、賞与等給与明細に列記されたすべての貨幣収入の月平均賃金のことをいう。
④ 経済補償金に対する個人所得税:従業員が取得した経済補償金の内、その地方の前年度の平均賃金の3倍を超える部分に対しては、個人所得税が課税されるので、会社は経済補償金を支払う前にその金額を天引きして代納しなければならない。経済補償金の金額が平均賃金の3倍を超えない場合は課税されない。
11、労働関係の解除
① 労働契約法には、労働契約を解除する場合、会社は30日前までに書面で従業員本人に通知するか、或いは別途1ヶ月分の賃金を支払わなければならないとしている。事前にきちんと準備をすすめ、できるだけ30日前の通知をするようにしたい。
② 労働関係解除協議書(一式二部)を作成し、会社と従業員の双方が署名し、各一部ずつ保管する。社会保険の脱退手続きの際に、この協議書の提出を求められる。
③ 会社は労働関係解除の日から15日以内に、当該従業員の人事档案届け、社会保険の移転或いは一時休止手続きをする。
以上、実際の運用に当たっては、各地の労働部門が労働契約法の個別の条項について異なる解釈をしている場面に出くわすことがある。そのため、従業員に解雇を通知する前に、個別のケースについて、現地の労働保障部門に問い合わせをして、できるだけその支持と協力を得られるようにしたい。
以 上